| TOP >shinsakai > |
| 「すべての人の社会」07年1月号 障害程度区分の策定経過への疑問 佐藤久夫 応益負担問題、報酬単価問題、日額制問題などにかき消されてあまり表面化してこなかった観のある「障害程度区分」であるが、障害者自立支援法の中心的な装置として非常に重要である事実に違いはない。 政府は障害程度区分を見直すために、やや規模を広げた「施設・在宅介護実態調査」を企画し、障害者の「心身の状況」と実際に「利用している介護サービス」の統計的関連を外からの観察によるタイムスタデイで把握しようとしたが、11月調査実施が延期されている。その理由は筆者には不明だが予想はできる。 障害者にとって必要な「介護」の概念や範囲についての吟味が十分ではない。また介護支援を外からどう観察できるのか。特定の人が視界にはいるとパニックを起こしかねない利用者のために、前の晩に丹念に作業スケジュールを調整する職員の活動を調査する視点はあるのか。障害者支援を知らない調査員が入り込んで、ある障害者への支援は何分だったと判断するのは失礼なこととも思われる。 「個別性、個人の尊重」をうたう法律に、「統計」を中核に据えるこの制度がなじむのであろうか。統計はバラツキを前提としたものであり、「個々の多様性」から「全体の傾向」を見るものである。その逆の使い方をしているのではないか。 一方政府は障害者基本計画で、人間と環境の相互作用を基本認識とするICFの活用を進めると決めたが、逆に環境を意図的に無視するシステムをニーズ把握の基本に据えてよいのかと思う。 他方、実際に審査を進める自治体レベルで、このシステムを揺るがす動きが進んでいる。政府は2006年8月の報告で、障害程度区分の試行事業に参加した(つまりよく理解している)全国60の市町村の平均変更率(コンピューターによる一次判定を変更する割合)が約3割だとした(平均しか公表せずバラツキは出していない)。いろいろな情報によれば、いま全国の市町村でこの変更率が2割以下のところから7−8割のところがある。2、3ランクアップも珍しくないところと、変更しても1ランクというところも。 公平性・画一性を目的に導入されたこの制度が、介護ニーズをできるだけ誠実に評価しようとする、つまり一次判定をあまり信用しない審査委員会によって、揺らぎつつある。 本稿では、この区分について、とくにその策定過程をふり返って検討する。 1 基礎となった厚生科学研究結果の解釈 政府は、2004年度の厚生科学研究(遠藤英俊班)によって、要介護認定は障害者の介護ニーズ判定にも有効であるが、訓練ニーズの判定には別のロジックが必要だという結論が導かれた、とする。しかしその研究とくに分担研究結果を検討すると、その有効性は部分的なものであり、とくに精神障害者には当てはまりがよくないというのが研究結果である。 2 2005年度試行事業の進め方と結果の解釈 上記理解に基づいて、2005年度の障害程度区分等試行事業は、一次判定(79項目による要介護認定)を大きく変更する必要はない、追加27項目は主に訓練等給付のニーズを見るためのものである、というメッセージ、バイアスのもとで実施された。例えば、27項目や医師意見書などから「大きく介護時間が変わる」とみられる場合にのみ一次判定の変更を検討せよという指示がなされている。 また参考例33のうち変更例は3例のみで、いずれもパニックや暴力行為などの行動障害の激しいケースであった。変更なし30例もほとんどが家事・買い物などのIADLや行動障害で支援を要するケースだった。国会などでは27項目を含めたので安心をといいながら、試行事業では極力これらを反映しないよう指示していたと言える。 試行事業では一次判定の変更率は全体では約50%で、「非該当」だった場合にのみ約80%と極端に高かった。この理由として、試行事業の審査会が「一次判定を変更しないように示唆されているものの、非該当のままではサービスが受けられなくてかわいそうだ」と判断したことが考えられる。試行事業の信頼度を低める数値である。 試行事業の結果を見ると、二次判定と実際に利用しているホームヘルプ時間の関係は、知的障害者ではほとんど相関はなく、精神障害者では全く相関はないというものであった(図1。厚労省障害保健福祉部「障害程度区分判定等試行事業の結果」(第29回社会保障審議会障害者部会、2005.12.5、資料2 参考))。したがって試行事業の結果を尊重するなら、これらの障害者にはこの認定システムを適用してはならないものであった。 さらに、障害者の特性を反映させるとして導入された認定調査の27項目が、79項目によるプロセス1の判定で区分3以上であった場合には一次判定に全く反映されないことが、どのように合理的に説明できるかという問題である。区分2以下にしか見られないような、介護時間を増加させる要因は常識的に考えられない。しかも、27項目中のIADLの7項目は一次判定で使われたのだから二次判定に使ってはならないとされる。試行事業からなぜこうした現場感覚と異なる結果が出たか非常に不透明である。 3 市町村審査会むけの情報提供のあり方 2006年8月24日に政府は、市町村審査会の参考にするために二次判定で不変更の27例と変更の17例を紹介した。前者では「行動障害や精神症状などがチェックされていても、二次判定で変更する必要はない」、後者では、「上方修正するには相当激しい精神症状か行動障害があること、あるいは知的障害と精神障害や聴覚障害などが合併していて激しい精神症状か行動障害を要すること」という制約的メッセージが伝わってくる。 後者の例として、気にくわないと包丁を振り回すなどのために何人ものグループホーム世話人を退職に追い込んできた知的障害者は一次判定の区分2が区分4へと2ランクアップされている。2ランクアップもありと例示した意義はあるとはいえ、このような支援の困難度が証明されなければ2ランクアップはないという示唆と多くの審査員は受けとめる。 そもそも区分毎の「基準時間」がだいぶ実態とかけ離れている。通所施設やグループホーム利用者は見守りや助言も含めて1日に最低でも2,3時間の支援の必要な人が一般的であろう。つまり基準時間で区分すればほとんどが区分6となって不思議はない。しかしほとんどが一次判定で区分1−3とされ、審査会が暗中模索で最終判定しているのが実情である。 4 おわりに 「障害者独自の27項目が組み込まれているので障害者のニーズは十分把握される」、は誤解であり、この認識では障害者にとって不利な二次判定・支給決定をもたらす可能性がある。当面審査会は、こうした現行システムの不備を二次審査で補う必要がある。 さらに根本的には、法の実施に伴って蓄積される情報を活かし、より適切な個別のニーズ評価システムを開発すべきである。 (より詳しい内容は障害者問題研究および日本社会事業大学研究紀要(いずれも2007年春発行予定)に投稿中の報告を参照のこと)。 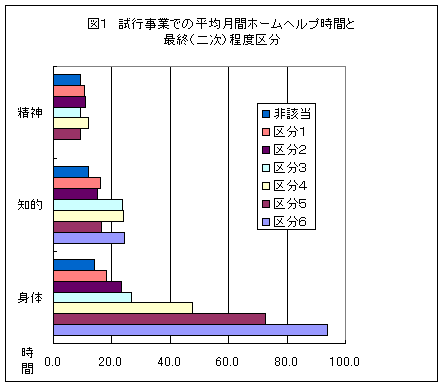 |
|
TOP > shinsakai > |